こんにちは、四姉妹のパパ、ラブドラです。
今日のテーマは妻の産後ストレスを解消させる方法についてです。
 パパ猫1
パパ猫1最近さぁ、嫁が変なのよぉ〜
常にイライラしたり、何もしてないのに怒ったり、もう嫌だニャア💦



子供生まれてから急に変わったニャ



兄弟産まれる度に妻がそういうのなるニャ
もう辛いニャ💦



パパさん達、頑張ってください!
妻の産後のストレスは誰もが通過する関門です。
今この記事を読んでいるパパさんは、産後の妻の変化に憤りを感じて、何とか乗り越えようと一生懸命になっているかと思います。
- 妻の産後のストレスを解消させる方法
- 産後のストレスの仕組み
- 産後のストレスによる離婚の危機
- 私の産後ストレス体験記
- とにかくお互いによく話す
- 妻の鬱憤の避雷針になる
- 妊娠中に好きになった食べ物をプレゼントする
- 一人になれる時間を作る
- 家事を積極的にやる
- 『辛いのは今だけ』とひたすら我慢する
私は4人の子どもの出生後、妻の産後のストレスに何度も悩みました。
妻の変化に悩むパパさんの気持ちは本当によくわかります。
そんなパパさん達の悩みに、少しでも貢献できればと思い記事を書きました。
覚えておいてください。
その辛さは今だけです。
今を越えれば、「あの時は辛かったねぇ」と妻と笑える日が必ず来るので、頑張って今を乗り越えてください。
今すぐにでも苦痛を和らげたい人は、下記の「私の体験記」だけでも読んで、少しでも苦痛を和らげて下さい。
それではどうぞ👋
夫のサポートで妻の産後ストレスを解消させる6つの方法
妻の産後のストレスを解消させる6つの方法について解説します。
なんで産後ストレスが起きるかなど、仕組みが知りたい方は読み飛ばしてください。


産後のストレスは
これらを全部やってもなくなるものではない
乗り越えるのに長い時間がかかる
ものなので、夫であるパパさんがしっかりとサポートしながらやっていきましょう。
1 とにかくお互いによく話す
この方法が1番大事です。
とにかくお互いに冷静になって話す時間をたくさん作りましょう!
少しでも妻と話して理解することが大切です。


妻も体調が安定している時には、冷静に話ができる時もあるので、
何であんなことしちゃったの?
疲れてるの?
など冷静に声をかけて話し合いましょう。



話し合った最後に妻が「なんであんなことしたのかわからない」と、涙ながらに話してきたこともありました。
産後うつはパパには理解し難いものですが、どの女性にも産後に当たり前なことなので、割り切って時間かけて話していきましょう。
2 妻の鬱憤の避雷針になる
産後のストレスを抱えた妻は、とにかく鬱憤が溜まっています。
どんなものにでもイライラして険悪感を抱いています。
そしてその矛先は
いつも身近にいて文句を言ってもいい存在のパパさん
に向けられます。
これ、パパさんはどうやっても逃げられないんです
こんな時は、どんな手を使ってもうまくいかないので、逆に諦めて妻の鬱憤の避雷針になりましょう。
つまり、自ら勧んで妻のイライラを受け止めるということです。
どうせうまくいかないんです。諦めて、妻の言いたいことを全部受け止めましょう。
うんうんそうだね、ごめんね
パパさんはそう言い続けて耐えましょう。
ちょっと辛い努力になりますが、やってみると結構効果があります。
3 妊娠中に好きになった食べ物をプレゼントする
妊娠を経て出産すると、妻の食事の好みも変わりますよね。
よくあるのが、レモンやグレープフルーツなどの柑橘類が好きになります。
妻の好みに合わせて、こういった気持ちの鎮まるプレゼントをすれば
ちゃんと気に掛けているよ
という気持ちも伝わり、妻も冷静になれます。
こう言った小さな努力を積み重ねることが大事です。
妻に対するプレゼントについては、この記事も参考にどうぞ


4 一人になれる時間を作る
生まれたばかりの子どもは一切目が離せないのでとても大変です。
妻はこの状況にとてもストレスを感じています。


そのため、子どもを妻から離して一人になれる時間を作りましょう。
ほんの少しの時間でも大丈夫です。
例えば、
ちょっと散歩しておいでよ
と言って、子どもを10分くらい預かるだけでも効果あります。
それだけでも妻は十分心が休まります。
5 家事を積極的にやる
妻はただでさえ子どもから目が離せないのに、料理に洗濯と、家事も大忙しです。
そこに出産後のストレスも加わってもうパンク状態です。
そんな時こそ、パパさんが家事を積極的にやりましょう。
むしろ、こんな時は全部の家事をやらなくてはいけません。
今は育児休暇がとりやすい時代になってきました。
パパさんは積極的に育児休暇を取得して、家事を全部こなして、ママさんのストレスを全力で緩和させましょう。
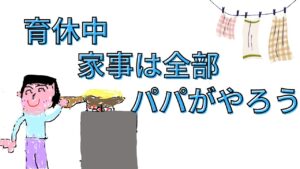
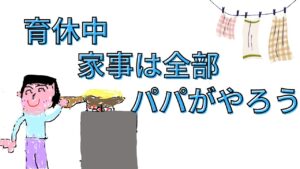
6 『辛いのは今だけ』とひたすら我慢する
妻の唯一の理解者であるパパさんなら、もう出産後のストレスについては、ひたすら我慢するしか方法がないのかもしれません。
辛いのは今だけです。「この時期はそういうもんなんだ」と無理矢理にでも自分の中で理解して下さい。
産後のストレスの仕組み
妻の産後のストレスについて、その仕組みを理解し、この危機を乗り越えましょう!
なぜ起こるのか理解すれば、パパさんの中で気持ちが落ち着いて、少し納得できると思いますよ。



産後のストレスの仕組みなんて…
子育ての大変さがストレスなだけニャ



もちろんそうなんですが、ホルモンバランスなどの理由もあるそうなんですよ。
妻の出産後のストレスは、一般的には「産後うつ」などとと言われているようです。
こちらの文はWikipediaから引用しました。
産後うつとは、主に出産後で産褥期の女性が出産で女性ホルモン(エストロゲン)が急激に減少することからセロトニンが減少するというホルモンバランスの崩れを主要因で発症する産後気分障害の一種。分娩後の数週間、人によっては数カ月後まで極度の悲しみ、それに伴う心理的障害が継続する
Wikipediaから引用
この引用した内容からすると、出産後のホルモンバランスの崩れが原因ので発生するようです。
このようなことが理由で発生するんだなと理解しておけば、少し自分を客観的に見て冷静になれませんか?
産後のストレスによる離婚の危機
次にこちらのグラフを見てください。
これは厚生労働省ホームページの平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告から引用した数字をグラフ化したものです。


このグラフは、簡単に言いますと末っ子が何歳の時に離婚して母子家庭になってしまったかを表したグラフです。



うわぁ〜、3歳になる前に離婚する人が1番多いニャ
そうなんです。
子どもが3歳になる前に離婚してる人が1番多いんですよ💦
「離婚原因は産後のストレスである」とはっきりとはわかりませんが、妻の産後のストレスにより離婚の危機にもなることも十分考えられますね。
体験記 私が妻からされたこと
私自身も産後の妻のストレスにより
もう離婚してしまうんじゃないか
という危機を体験しました。
こんな生活だったら離婚した方がマシかも
なんて思ってしまった時期もありました。
私の場合は、産後の妻のストレスの矛先が全部パパに向けられました。
一人目の娘が産まれた時、私は妻と子どもとアパート暮らしをしていました。
出産後、みなさんと同じように、妻は産後のストレスに苦しんでいました。
当時、私は妻のストレスを全て受け止める立場になっており、妻から
- 毎日冷たい目で見られる
- 何を話しても無視される
- 寒い真冬の夜中に掛け布団を剥がされた
- ご飯が夫のだけ質素になる、時には作ってくれない
といった、辛い仕打ちを受けてしまいました。



うぅ…
なんでそんなことするのかニャア



理解できないことをするのもストレスの内なんだなと自分に言い聞かせました。
この頃は、ストレスの解消先が私しかいなかったわけです。
私が後日、妻に「当時はなぜあんなことをしたのか」と聞くと、妻は「よくわからない」と言ってました。
とても理解できない回答ですが
今となってはもう過ぎたことで、乗り越えたことだからどうでもよいこと
なんです。
今私は妻と子どもと楽しく幸せな毎日を過ごしてますし、「あの辛い日々を乗り越えたな」って気持ちが日々パパとして頑張る支えとなっています。
結果オーライなので、どうでもいいことです。


私からイクメンパパたちに言いたいことは、
辛いのは今だけだからひたすら我慢してほしい
とにかく妻を信じて理解してほしい
離婚だけは絶対にしないでほしい
ということだけです。
終わりに
この記事では夫のサポートで妻の産後のストレスを解消させる方法について学びました。
- とにかくお互いによく話す
- 妻の鬱憤の避雷針になる
- 妊娠中に好きになった食べ物をプレゼントする
- 一人になれる時間を作る
- 家事を積極的にやる
- 『辛いのは今だけ』とひたすら我慢する
正直、しっかりと解消できる対策ではないですし、どれも我慢することばかりなので、ガッカリしたパパさんもいるかもしれませんね。
しかし、私はこの夫婦の問題は
夫としてパパさんがひたすら我慢して乗り越えるしかない
というのが最終的な答えだと思ってます。
辛い時期ですが、我慢して乗り越えた先に、妻や子どもと笑い合える円満な家庭が待っています。
辛い経験を共にした分だけ、絆が深まりますよね?
十分な対策とは言えないですが、これらを参考に今を乗り切り、笑い合える家庭を目指しましょう。
オススメ記事紹介
夫婦関係において我慢はとても大事です。
その我慢大の切さは、ぜひ子どもの教育でも教えてあげてください。
実は我慢は、子どもの成長に大いに関係あるものなんです!
ぜひこの記事にも目を通して、我が子の成長の参考としてください👇


にほんブログ村ランキングにも参加しています。


コメント